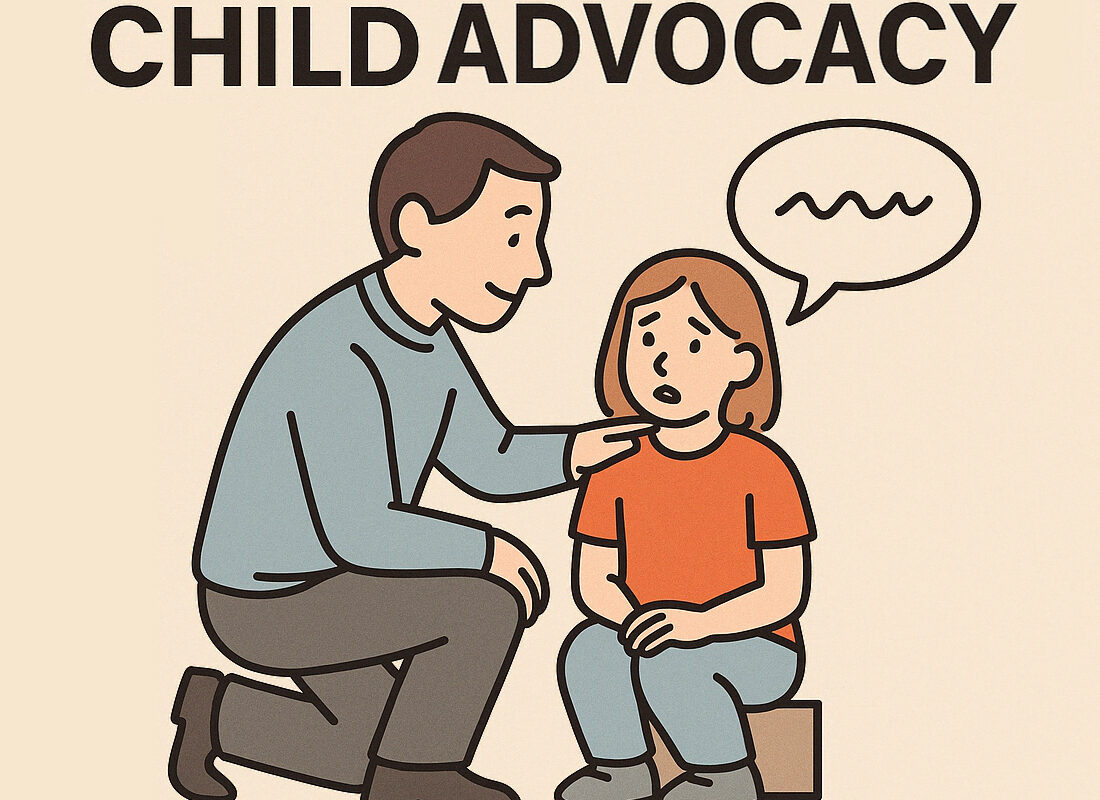4月17日、茨城県議会公明党の村本修司議員の活動が、公明新聞に紹介されました。
村本議員は、社会的に弱い立場にある子どもの声を第三者が聞き取って意見を代弁する「子どもアドボカシー」制度の普及に取り組んでいます。以下、公明新聞の記事を引用します。
「子どもアドボカシー」始動 声を聴き気持ち代弁/茨城県
公明新聞2025/04/17付け
社会的に弱い立場にある子どもの声を第三者が聞き取って意見を代弁する「子どもアドボカシー」の試みが、茨城県で昨年秋以降、本格化している。推進する公明党の村本修司県議はこのほど、同事業を受託している茨城県公認心理師協会の杉江好子副会長らから活動状況などを聞いた。
■児相の一時保護所に支援員派遣
茨城県は現在、児童相談所の一時保護所や民間の一時保護専用施設など県内5カ所に「アドボケイト」と呼ばれる支援員を派遣。一時保護所では今年1月までに約40人の子どもと面談し、「この先どうなるのか詳しく知りたい」「お世話になった職員に手紙を書きたい」といった声を受け止めた。
アドボケイトを務める杉江副会長は、一緒に折り紙を作って遊んだりする中で、子どもたちから面談の希望が増えたと話す。「『話を聞いてほしい』という子が予想以上に多い。親でも職員でもない第三者の気楽さがあって、話しやすいのかもしれない」と振り返る。
杉江副会長をはじめ、県公認心理師協会に所属する22人がアドボケイトの基礎研修を修了し、県から認定を受けている。スクールカウンセラーの経験者も多く、聞き役に適している。一方で、杉江副会長は「アドボケイトは、子どもたちの『マイク』になることが大切。ケアや分析ではなく、ありのままの思いをくみ取る役目に徹したい」と強調していた。
県は普及策の一環として児童養護施設の児童らに配布する「子どものための権利ノート」を改定。アドボケイトに話や考えを聞いてもらえる「意見表明等支援制度」について分かりやすく説明している。
村本議員は、虐待などに苦しむ子どもたちに寄り添い、声を受け止める仕組みとしてアドボケイトによる支援制度の導入を4年前から繰り返し議会で主張してきた。「アドボケイトの育成や県民への啓発を引き続き後押ししていきたい」と語る。
子どもの意見を尊重する「子どもアドボカシー」とは
子どもアドボカシーとは、子どもが意見や考えを表明できるようにサポートすること。アドボカシー(advocacy)は、ラテン語の「voco(声を上げる)」に由来します。
子どもアドボカシーを実践する人を「アドボケイト」といいます。現段階では公的な資格はありませんが、NPO法人などがアドボケイトの養成講座を実施しています。
アドボケイトの特徴の1つは、保護者や学校など子どもに関わる人や組織から完全に独立していること。もしアドボケイトがどこかの組織と密接に関係しているのであれば、子どもはその組織に気を遣い、アドボケイトに本音を話せないかもしれません。
子どもアドボケイトは、子どもが意見を表明する権利を支えるために存在するので、完全に独立している必要があるのです。
子どもアドボカシーの対象は、社会的養護の子どもがメインとなります。
児童福祉法の改正により、2024年から「児童の意見聴取等の仕組みの整備」が実施されます。これによって、児童養護施設や一時保護施設の子どもたちへの措置を検討する際、子どもの意見を聞くことが盛り込まれました。
しかし、社会的養護の子どもに限らず、家庭の中にもなかなか自分の声を聞いてもらえないと感じている子どもはいるはず。子どもの声を社会に反映させるためには、あらゆる子どもに対して子どもアドボカシーが必要です。
保護者や教師など子どもに関わる全ての人が子どもアドボカシーについて理解し、子どもの声を聞くことで、子どもを尊重した社会を実現できるのです。