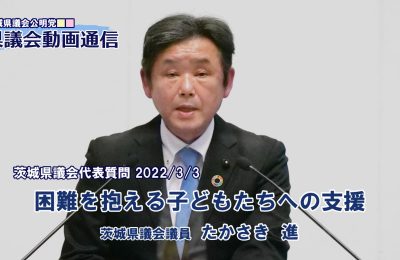2025年の「こどもの日」を迎えるにあたり、茨城県の子どもたちの現状と、子どもの子どもの権利を守る県議会公明党の姿勢について改めて考えてみたいと思います。
現在、茨城県に住む15歳未満の子どもの数は29万8,222人となり、総人口に占める割合は10.9%にまで低下しました。この数値は、大正9年に国勢調査が始まって以来、人口・割合ともに過去最低となっています。とりわけ注目されるのは、子ども人口の地域差です。つくば市や守谷市のように子育て世代の流入が続く市では子どもの割合が15%前後と比較的高い一方で、利根町や大子町などでは6%台にとどまり、急速な人口減少と高齢化が深刻な課題となっています。
また、令和5年の茨城県の出生数は1万4,898人で、前年より1,007人減少し、合計特殊出生率も過去最低の1.22を記録しました。これは単に統計上の問題にとどまらず、地域社会の活力や将来の担い手をどう確保するかという、きわめて根本的な課題です。
こうした状況の下、子ども権利を守る取り組みは非常に重要な政治の使命です。
「子どもは権利の主体である」――これは、1994年に日本が批准した国連「子どもの権利条約」の根幹をなす考え方です。教育や医療を受ける権利だけではなく、意見を述べる権利、自分らしく生きる権利、そして何よりも尊重される権利を、すべての子どもが保障されるべきだという理念がそこにはあります。
2023年には、こうした理念を国内法として定着させる「こども基本法」が施行されました。これは、子ども政策の司令塔である「こども家庭庁」の創設とあわせて、国がようやく子どもを真ん中に置いた政策転換をはじめた大きな一歩でもありました。しかし、法律ができたからといって、子どもたちの声がすぐに社会に届くようになるわけではありません。今こそ問われているのは、「どう運用し、どう実現していくか」という地方政治と現場の実行力です。
茨城県議会においても、公明党は「こどもまんなか社会」の実現を掲げ、さまざまな取り組みを進めています。なかでも注目されるのが、「子どもアドボカシー(意見表明支援)」の推進です。子ども自身が、自らの考えや気持ちを表明できるように支援する仕組みであり、学校や児童相談所などにおいて、子どもが一方的に決定を押し付けられるのではなく、十分に対話の機会が与えられるようにするための制度です。公明党はこのアドボカシー制度の整備に向けて、専門の支援者である「子どもアドボケイト」の育成や、第三者性のある相談・代弁体制の確立を強く訴えてきました。
また、意見表明だけでなく「居場所の保障」も大切な子どもの権利です。家庭や学校で安心できる場所を持てない子どもたちが、地域に開かれた居場所を見つけられるように――この思いのもと、茨城県内では子ども食堂や地域交流拠点、フリースクールなどの支援が徐々に広がっています。公明党は、こうした活動を一過性の福祉施策ではなく、子どもが自らの居場所を選ぶ権利として捉え、継続的な支援と法的位置づけの強化を求めています。
さらには、教育環境の整備も「学ぶ権利」を保障する上で欠かせません。猛暑への備えとして、特別教室や体育館への空調設備の整備を推進することは、身体的な安全の確保だけでなく、障がいのある子どもや体調に不安を抱える子どもたちの学習権を守るうえでも重要です。平時から使えて災害時にも役立つ「フェーズフリー」の観点を踏まえ、公明党はこうした設備投資を「命を守るインフラ」として位置づけています。
これらの取り組みはいずれも、単なる支援ではなく、「子ども自身が自分の人生を生きるための権利をどう支えるか」という視点に立っています。時代が変わり、家族の形も地域のあり方も多様化する中で、「すべての子どもが尊重され、声が届く社会」を築くことは、今を生きる大人たちの責任にほかなりません。