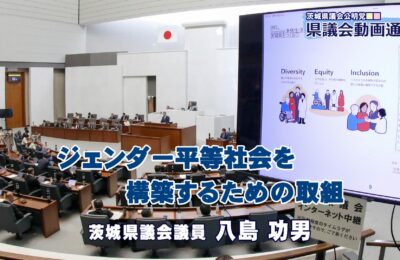国連児童基金(ユニセフ)のイノチェンティ研究所は2025年5月、先進国・欧州43か国(日本を含む)の子どもの幸福度を調べた報告書「レポートカード19」を発表しました。
この調査では、子どもの幸福度を「身体的健康」「精神的幸福度」「スキル(学力や社会性)」の3分野で評価しています。日本の総合順位は36か国中14位に上昇しましたが、精神的幸福度(子どもの生活満足度や自殺率を指標にしたもの)は36か国中32位と、依然として低い結果でした。
日本では、15歳時の生活満足度が低い一方で、自殺率が高いことが示されています。その背景には、親子の会話時間が短いことや過度な受験競争、SNSによる情報過多、そして地域で孤立しやすい環境などがあると指摘されています。
実際、厚生労働省の統計でも、10代の子どもの自殺者はここ数年500人前後と高い水準が続いており、深刻な問題となっています。
茨城県においても、子どもの精神的ケアや学びの支援は非常に重要な課題です。県は2025年度から2029年度までの5年間を対象に、子ども政策の総合計画「茨城県こども計画」を策定しました。
この計画は、「子どもまんなか社会」の実現を目指し、子どもの安全・安心や学びの機会を一体的に支えることを柱としています。また、県や市町村は自殺対策にも取り組んでおり、茨城県では「第2次自殺対策アクションプラン」を策定し、2025年までに自殺率(人口10万人あたり)を10.4以下に下げる目標を掲げています。
県の公表資料によれば、県内の20歳未満の自殺者数は2020年頃から年間20人前後で推移しており、改善の余地が大きい状況です。
こうした課題に対して、学校や地域では子どもたちが安心して過ごせる環境づくりが進められています。
県教育委員会はスクールカウンセラーの配置事業を実施しており、臨床心理士や公認心理師らを公立学校に配置し、いじめや不登校などに対応しています。これにより、児童・生徒への個別カウンセリングや保護者・教師への助言・研修を通じて、心のケアを行う体制が整えられています。
さらに、スクールソーシャルワーカー(社会福祉士など)も学校に派遣されており、家庭環境や福祉の専門的視点から支援し、学校と福祉機関をつなぐ役割を担っています。これらの施策は、子どもの問題を早期に見つけて適切に対処するためのチーム体制の強化に繋がっています。
学力や学習支援の面でも、県内各地で取り組みが進められています。たとえば、つくば市では経済的に困難な家庭の子どもを対象に、無料学習会「つくばこどもの青い羽根学習会」を開設し、ボランティア講師による学習支援や居場所づくりが行われています。
また、龍ケ崎市でもNPOと連携し、無料塾形式の学習支援事業を市の予算で実施しています。これらの教室では、「勉強がわからない」「話せる大人がほしい」といった子どもの声に応え、学習指導だけでなく、心の悩みにも寄り添っています。いずれの取り組みも、経済的負担を減らし、子どもたちが安心して学べる場を提供することを目的としています。
今後は、こうした施策をさらに広げていくことが必要です。子どもの心身の安全と学びの機会の両立を実現するには、学校や地域での居場所づくりを推進し、いじめや孤立を防ぐ取り組みを強化することが求められます。
スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの配置を拡充し、子どもたちが日常的に相談できる体制を整えることが重要です。若者向けには、スマートフォンやSNSを活用したオンライン相談窓口や電話相談の充実を図り、専門家による支援につなげることが求められます。
また、教育面では高校までの授業料無償化(高校無償化)や奨学金制度の充実を進め、家庭の経済状況にかかわらず誰もが学び続けられる環境を保障することが不可欠です。
地域独自の取り組みも大切です。茨城県内では、NPOが運営する子ども食堂や学習支援ネットワークが広がりつつあります。これらは、子どもが自宅以外で安心できる居場所を提供し、地域コミュニティで子育てを支える仕組みとして注目されています。
県や市と民間団体が連携し、こうした活動を支援・拡充することで、格差の是正や孤立の防止に繋げていく必要があります。
全国的に見ても、子どもの精神的幸福度を高めるためには、「学び」と「安心」を両立する総合的な支援が欠かせません。
茨城県では「こども計画」や「自殺対策計画」を背景に、学校・家庭・地域が連携した支援策が前進しつつあります。今後は、保護者や地域住民の理解と協力を得ながら、子ども一人ひとりが安心して成長できる環境を築くため、きめ細やかな施策の展開が期待されます。
茨城県こども計画(2025年版)https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/kodomo/shoshi/documents/keikakuhontai.pdf